はじめに
ここ数年で「副業解禁」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
政府の働き方改革や、企業による柔軟な働き方の推進などを背景に、副業を許可・推奨する企業も少しずつ増えてきています。
また、物価の上昇や将来への不安から、「今の給料だけでは不安…」「自分のスキルを活かして収入を増やしたい」と考える人も多く、副業への関心は年々高まっています。
しかし現実には、副業をしていることを「会社にはバレたくない」と考えている人が大多数です。理由は様々ですが、以下のようなものがよく挙げられます。
- 会社が副業を禁止している
- 周囲に知られたくない
- 人事評価やキャリアに悪影響が出そう
- バレたときにトラブルになるのが怖い
副業は自由な働き方を実現する手段である一方で、「ルールや税金をよく知らずに始めてしまうと、思わぬ落とし穴がある」というのも事実です。
このブログでは、会社にバレずに副業を行うために必要な「税金」と「法律」の基礎知識を、初心者の方にもわかりやすく解説します。
- なぜ副業がバレるのか
- 住民税のしくみと回避策
- 副業に必要な確定申告のポイント
- 就業規則や法律に違反しないための注意点
など、知っておくべき大事なことを丁寧にお伝えします。この記事を読めば、「何も知らずに副業を始めて会社にバレてしまった…!」という事態を避けるための知識が身につきます。
なぜ副業が会社にバレるのか?
「会社にバレないように副業したい」と思っていても、意外なところから情報が漏れてしまうことがあります。
この章では、どのようなルートで副業がバレてしまうのか、そして実際のバレた事例なども交えて解説します。
副業がバレる主な3つのルート
① 住民税の通知からバレる
これが最も多いと言われるケースです。
副業で得た収入には所得税だけでなく、住民税もかかります。副業分の住民税も含めた金額が「給与天引き(特別徴収)」として会社に通知されると、
「あれ?この人の住民税、高くない?」
と、会社の経理や人事が気づく可能性があります。
会社側は従業員の年収を把握しているため、それと合わない住民税の額が来ると「何か他にも収入があるな」と疑われてしまうのです。
➡この問題を防ぐには、住民税を「普通徴収」にすることが重要です。
(詳しくは第3章で解説します)
② SNSやブログ、YouTubeなどネット上の活動からバレる
自分の名前で副業活動をしていたり、顔出しをしていたりすると、ネットで偶然見つかってしまうリスクがあります。
特に以下のようなケースは注意が必要です。
- 副業で書いたブログ記事に本名を載せていた
- SNSアカウントで職場の話題を投稿していた
- YouTubeで顔出しして商品レビューしていた
たとえ本名を使っていなくても、声や見た目、話し方、投稿内容から本人が特定されるケースもあります。ネットは広くて深いですが、意外なところから会社の人に見つかることがあります。
③ 同僚や取引先からの情報漏れ
副業をしていることをうっかり話してしまったり、信頼して話した相手が他の人に漏らしてしまったりするケースも少なくありません。
たとえば、
- 飲み会の席で「実は副業やっててさ~」と話してしまった
- SNSでつながっている同僚が副業アカウントを発見
- 取引先の会社が自分の本業先とつながっていた
など、人づてにバレるルートも存在します。
特に副業で同業界に関わる仕事をしている場合は、業界内でのつながりや情報が予想以上に広がっている可能性もあります。
実際にバレた人の事例
事例①:Webライターとして活動→住民税で発覚
会社員Aさんは、副業として夜間にWebライターの仕事を受けていました。
収入も月5万円ほどあり、年間では60万円近くに。翌年、住民税の金額が急に上がり、会社の経理担当が不審に思い調査した結果、副業がバレてしまいました。
➡ 原因:住民税を「特別徴収」にしてしまった
事例②:SNSで趣味のアカウント運用→同僚に見つかる
会社員Bさんは、副業でハンドメイド作品を販売。
Instagramで活動していたところ、共通の趣味を持つ同僚にフォローされ、活動内容を見られてバレてしまいました。
➡ 原因:副業アカウントに顔写真や職場の話題が載っていた
バレる理由を知ってリスクを下げよう
副業がバレる理由には「税金」「ネット活動」「人間関係」の3つのルートがあります。
逆に言えば、これらのルートをしっかり対策すれば、副業がバレるリスクを大きく下げることができます。
次の章では、副業に関わる「税金の基礎知識」について、初心者にもわかりやすく解説します。
副業と税金の基本
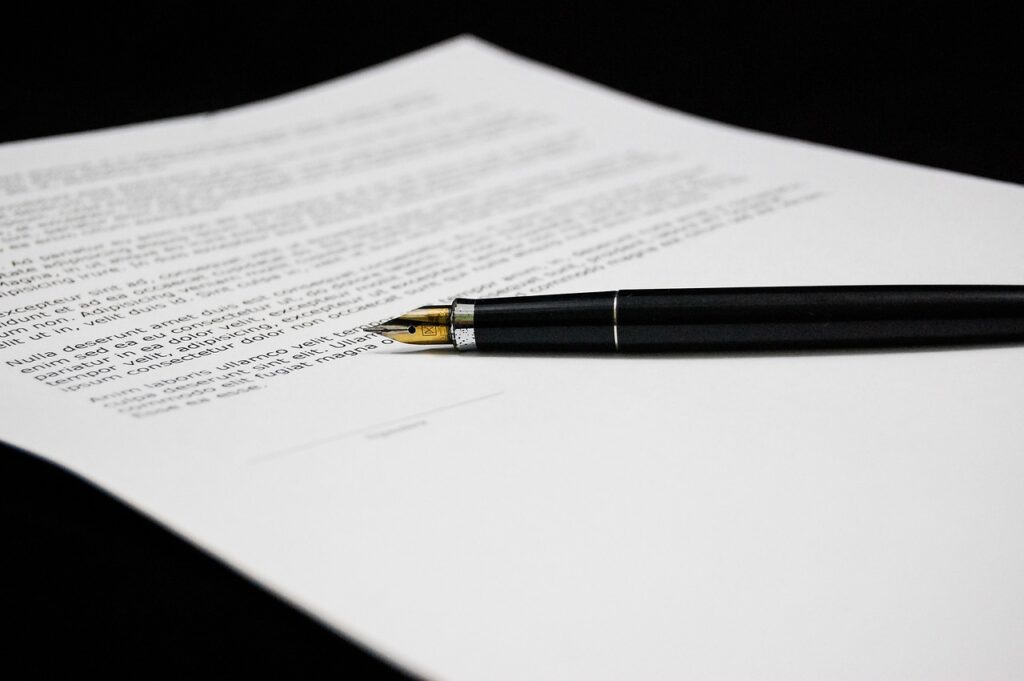
副業を始めるうえで、「税金のしくみ」を理解することはとても大切です。
知らないまま収入を得てしまうと、あとから税務署から連絡が来たり、思わぬトラブルにつながったりすることもあります。
この章では、副業で発生する主な税金や、確定申告の必要性など、基本的な知識をわかりやすく解説します。
副業にかかる税金とは?
副業で収入を得ると、基本的に以下の2つの税金が発生します。
● 所得税(しょとくぜい)
国に納める税金です。副業で得た「所得(=収入-経費)」に対して課税されます。
本業の給与と合算して税額が決まるため、副業収入が増えれば増えるほど、本業の税金も上がる可能性があります。
● 住民税(じゅうみんぜい)
市区町村に納める税金です。前年の所得に基づいて計算され、翌年に課税されます。
副業分の所得が増えると、住民税もその分高くなります。
この住民税の通知が会社に送られることで副業がバレることが多いです。
確定申告が必要になるのはどんなとき?
副業をしていても、必ずしも確定申告が必要とは限りません。
しかし、次の条件に当てはまる人は、原則として確定申告が必要になります。
✅ 年間20万円を超える副業所得がある人
副業で得た「所得」が年間20万円を超える場合は、確定申告をしなければなりません。
❗ここで注意
「収入」ではなく「所得(収入-経費)」で考えることが大切です。
たとえば、以下のような計算になります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 副業の収入 | 50万円 |
| 経費(道具、交通費など) | 35万円 |
| 所得(収入−経費) | 15万円(←申告不要) |
このように、経費をしっかり計上すれば、「申告が不要なライン」に抑えられることもあります。
所得の区分とは?
副業の収入は、どういう種類の所得かによって扱いが変わります。主に以下の2つに分類されます。
■ 雑所得(ざつしょとく)
- 一般的な副業(ライター、YouTube、せどり、アフィリエイトなど)はこちらに分類されます。
- 経費を差し引いた「所得」が課税対象です。
- 青色申告のような特別な節税制度は使えません。
■ 事業所得(じぎょうしょとく)
- 副業であっても、継続的に仕事として行っていて、規模もある程度ある場合はこちらになります。
- 事業として認められると、青色申告が使えるようになり、最大65万円の控除などの特典があります。
💡ポイント:副業を「事業所得」として認めてもらうには、事業性や継続性を示す証拠(開業届、帳簿、契約書など)が必要です。
税金に関する「よくある勘違い」
最後に、副業を始めたばかりの方がよくしてしまう勘違いをまとめておきます。
| 勘違い内容 | 実際は… |
|---|---|
| 「副業はバレなければ申告しなくてOK」 | 法律上は、所得があれば申告義務があります |
| 「収入が少ないから大丈夫」 | 所得が20万円を超えると、申告が必要です |
| 「確定申告すれば会社にはバレない」 | 確定申告の方法次第では、会社に通知がいきます |
副業と税金まとめ
副業をするなら、「所得税」と「住民税」がかかること、そして年間20万円を超える所得があれば確定申告が必要になることをしっかり理解しておきましょう。
また、所得の種類によって税金の扱いも変わるので、自分の副業がどの所得区分に当たるかを確認することも大切です。
住民税を普通徴収にする方法
「副業が会社にバレる最大の原因」と言われているのが、住民税の通知です。
この章では、住民税の仕組みと「普通徴収」と「特別徴収」の違い、そして副業分の住民税を自分で納付(普通徴収)する方法について、わかりやすく解説します。
なぜ住民税で副業がバレるの?
住民税は、前年の所得に応じて課税される市区町村税です。
会社員の場合、基本的に住民税は毎月の給料から天引き(=特別徴収)されています。
ところが、副業で得た収入にも住民税がかかるため、副業分の住民税まで含めた金額が会社に通知されるのです。
すると、会社の経理担当者はこう思うわけです:
「この人の年収にしては、住民税の金額が明らかに多いな…何か副収入があるのか?」
これが副業が会社にバレる典型的なパターンです。
「特別徴収」と「普通徴収」の違い
住民税の納税方法には2種類あります。
| 区分 | 内容 | 誰が納める? |
|---|---|---|
| 特別徴収 | 会社が毎月の給与から天引きして納める方法 | 会社が本人の代わりに納付 |
| 普通徴収 | 自分で納付書を使って支払う方法 | 本人が自分で納める |
副業による収入の住民税は、普通徴収にすることで、会社に通知が行かなくなり、バレるリスクを減らすことができます。
確定申告時に「普通徴収」を選ぶ方法
副業分の住民税を「普通徴収」にするためには、確定申告のときに選択する必要があります。
申告書の中に、住民税に関する項目があります。
【記入方法】(紙の申告書の場合)
確定申告書 第二表の中にある、
「住民税・事業税に関する事項」
という欄を見てください。
その中に、
- 「給与所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」
- □ 特別徴収(勤務先からの天引き)
- ■ 普通徴収(自分で納付)
という選択肢があります。
ここで、「普通徴収」に✔(チェック)を入れることで、会社には通知がいかず、自分で納付書を使って支払うことができます。
【e-Tax(電子申告)の場合】
e-Taxを使って申告する場合も、同様に「住民税の徴収方法」の欄で「普通徴収」を選べる画面が出てきます。忘れずに設定しましょう。
普通徴収を認めないケースも…
実は、一部の自治体では、普通徴収の希望が通らないケースも報告されています。
特に、副業所得が「雑所得」であっても、事業所得として申告していた場合や、所得の金額が大きい場合などに、住民税の通知が会社に行ってしまうことがあります。
対策は?
- 申告書の記載ミスを防ぐ(必ず「普通徴収」に✔)
- 不安な場合は、申告後に市区町村の税務課に電話して確認する
- 「住民税は自分で納付したい」と伝えておく
など、申告後の確認作業が安心につながります。
住民税の普通徴収まとめ
副業が会社にバレるのを防ぐには、住民税の「普通徴収」への切り替えが非常に重要です。
確定申告の際に「普通徴収」を正しく選び、自分で納付することで、会社に副業の収入が通知されるリスクを避けることができます。
ただし、自治体によっては例外もあるため、必要に応じて事前・事後に確認をしておくとより安心です。
副業が禁止されている会社のリスクと対策
副業を始める前に、必ず確認しておきたいのが「会社の就業規則」です。
現在は副業を推奨・容認する企業も増えてきましたが、まだまだ副業を禁止している会社も多く存在します。
この章では、副業が禁止されている会社で副業をした場合のリスクと、バレないための対策について詳しく紹介します。
まずは「就業規則」を確認しよう
就業規則(しゅうぎょうきそく)とは、会社が定める働く上でのルールブックのようなものです。
そこには、次のような記載があることがあります:
- 副業を全面禁止
- 許可制(会社に届け出・承認が必要)
- 業務に支障がない範囲で認める
✅ ここをチェック!
「職務専念義務に反する副業を禁止する」
「会社に無断で副業を行った場合は懲戒処分の対象とする」
このような文言がある場合、無断で副業をすると規則違反になってしまいます。
副業禁止に違反するとどうなる?
就業規則に違反して副業を行った場合、以下のような処分リスクがあります。
● 懲戒処分(けん責・減給・出勤停止など)
軽度の違反であれば「注意」「始末書提出」などの対応で済むケースもありますが、繰り返し違反したり、副業によって業務に支障をきたした場合は、より重い処分を受ける可能性があります。
● 最悪、懲戒解雇になることも…
副業が会社の利益と競合していたり、機密情報を利用していた場合などは、「重大な背信行為」とみなされ、懲戒解雇の対象になることもあります。
副業の内容によってもリスクは変わる
すべての副業が同じリスクを持つわけではありません。
たとえば、以下のようなポイントで、リスクの大きさが変わってきます。
| 副業の特徴 | リスクの高さ |
|---|---|
| 本業とまったく関係ない趣味系(例:ハンドメイド) | 低い |
| 業務時間外、短時間でできる仕事(例:ブログ) | 低め |
| 同業他社での業務、競合行為 | 高い(注意!) |
| 取引先との兼業、情報の持ち出し | 非常に高い(禁止) |
「副業=すべてダメ」ではない会社も多いため、内容次第ではOKになるケースもあります。
バレないための基本行動5選
副業が禁止されている環境で、どうしても副業をしたい場合は、次のような行動を心がけましょう。
① 本名や会社名を出さない
副業で使うアカウントやサイト、名義には個人情報を出さないことが鉄則です。
SNSや販売サイトで不用意に本名を出すと、検索で見つかるリスクが高くなります。
② 就業時間中は絶対に副業をしない
勤務時間中に副業を行うのは、職務専念義務違反にあたります。
業務に支障が出ると一気にバレる可能性が高まるので注意。
③ 職場の人に絶対に話さない
たとえ仲の良い同僚であっても、副業の話はしないのが原則です。
口は災いの元。うっかり話したことが社内に広がってしまうことも。
④ 副業の収入・税金は自分で管理する
確定申告や住民税の納付をきちんと自分で行うことで、会社に知られるリスクを減らせます(第2・3章参照)。
⑤ 本業に影響を出さない
最も重要なのは、「本業に影響が出ないようにすること」。勤務態度が悪くなったり、仕事のパフォーマンスが落ちると、「何か副業でもしてるんじゃ?」と疑われることがあります。
リスクと対策まとめ
副業が禁止されている会社で副業を行うことには、就業規則違反のリスクがあります。
最悪の場合、懲戒処分や解雇につながる可能性もあるため、ルールをよく確認し、リスクを理解した上で行動することが大切です。
とはいえ、内容や方法によってはリスクを最小限に抑えることも可能です。
次の章では、副業に関わる法律面の注意点についてさらに詳しく解説していきます。
最後に
「副業=バレないようにこっそりやるもの」と考えるのではなく、ルールとリスクを正しく理解した上で、トラブルのない形で行うことが、本当に長く続けられる副業の秘訣です。
もちろん、副業を続けていく中で、
- 所得が増えた
- 事業化したくなった
- 法人化や開業届を検討している
といったステップアップのタイミングが来たら、税理士や社労士などの専門家に相談することも選択肢に入れましょう。
副業は、あなたの可能性を広げる一歩です。
正しい知識と、少しの注意を持つことで、会社にバレるリスクを避けながら、安心して活動を続けることができます。
焦らず、一歩ずつ。
あなたの副業ライフが充実したものになりますように!
では( ˘ω˘ )
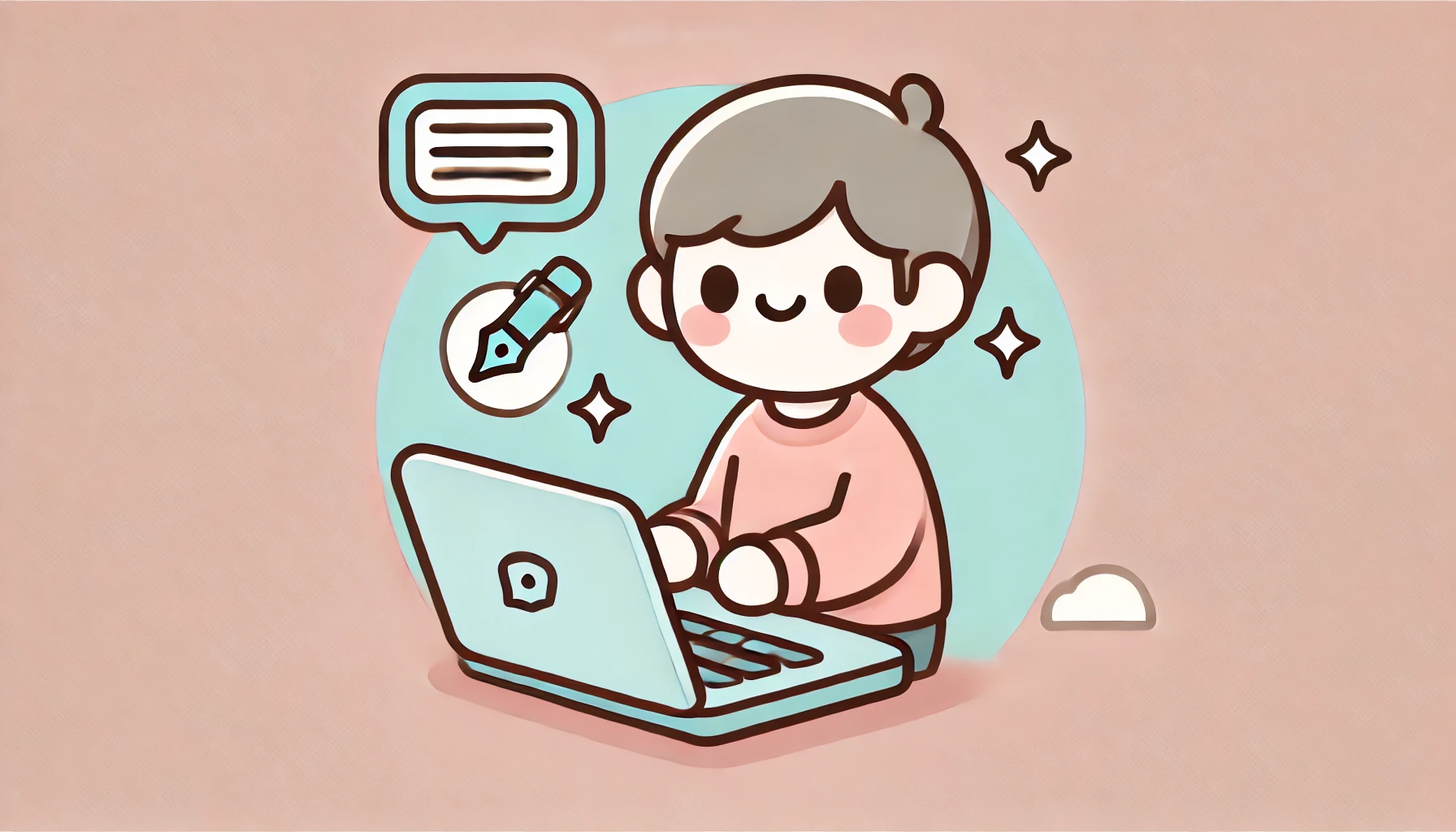


コメント